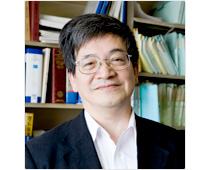ユニーク&エキサイティング研究探訪
No.01 レーザー新世代研究センターのセラミックレーザー研究
セラミックレーザー開発の原点は重力波研究
レーザー新世代研究 センター センター長
植田 憲一 教授
レーザー新世代研究センター所長の植田憲一教授がさきごろ平成21年度科学技術分野の文部科学大臣賞を受賞した。永年に渡るセラミックレーザーの研究に対する貢献を、共同研究者の神島化学工業・柳谷高公氏と一緒に顕彰された。
レーザー発振素子にセラミックを使うという考えは、レーザー発振が初めて成功した1960年代当時にあったという。しかし、当時のセラミック製造技術ではレーザー発振できるような透明なセラミックはできず、以来30年以上の間、セラミックがレーザー素子になることはなかった。植田教授らは、まったく新しい手法で透明なセラミックを開発、固体レーザーとして単結晶を上回る高性能セラミックレーザーを開発することに成功した。セラミックレーザーは、後追い開発ではなく、完全に日本オリジナルな研究成果で、植田教授は「セラミックレーザー・シンポジウム」国際会議を自ら創設してこの分野をリードしている。
植田教授らのセラミックレーザーの研究は、1991年に始まった。なぜ、30年も放置されていたセラミックに目を向けたのか。それには、重力波観測という、人間と宇宙との究極のコミュニケーションを目指す純粋科学研究が深くかかわっている。
植田氏がセンター長を務める電通大レーザー新世代研究センターは発足当初レーザー核融合の研究からスタートしたという。ただ、研究センターは時限付きであり、10年ごとに新たな概算要求で新設しなければならない。そこで植田氏は全く新しい研究展開を試みた。なんとそれが重力波観測。アインシュタインが一般相対性理論で存在を予測した重力波を直接観測しようとする試みである。それを可能にするには、従来とはケタ違いに雑音の少ない高安定なレーザーが必要だった。そこで研究を一から見直す中で、植田氏のアンテナに引っかかってきたのが、神島化学工業の柳谷氏の透明セラミック作成技術だった。1991年のことである。
化学的にナノ結晶を作りそれを仮焼する新手法
柳谷氏の手法は、純粋に化学的な手法で20nmサイズの単結晶を作り、それを仮焼して200nmサイズのナノ結晶を作る。それを型にいれて固めて真空焼成してセラミックを作るという手法だ。粘土状の酸化物粉末を焼成しながら化学反応させてセラミックを作る従来の手法とは全く異なるものだった。
神島化学工業は耐火外壁などを作っている会社で、当時はレーザーとは全く無縁な会社だったが、植田氏はその新しいセラミック製造技術に、セラミックレーザーの大きな可能性を直感し、共同研究(注1)を持ちかけたという。
1年ほどの共同研究ですぐかなり透明な材料ができたが、やや散乱が大きく、レーザー発振の実験はしなかったという。その後、日本ではバブル経済が弾けて、いったん中断した。ところがその間、1995年に当時黒崎窯業の研究者だった池末明生氏が、従来手法で作ったセラミックを半導体レーザーで励起してレーザー発振に成功した。ただしこれは従来の焼成手法で作ったセラミックを使っているため、効率の向上が難しかった。
植田教授らはバブル騒ぎが一段落した1999年に共同研究を再開、翌年に効率60%という単結晶に匹敵するセラミックレーザーを発表、さらに2001年には出力を1.5kWまで高めることに成功した。このためには、固体レーザー材料の生き字引であり、永年の友人であるロシア科学アカデミーのカミンスキー教授を引き込んだ国際共同研究ネットワークを形成したことも、大きな役割を果たした。
性能が単結晶を上回る
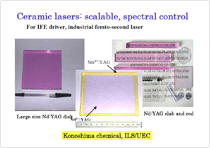
- セラミックレーザー
そして2004年、出力は110Wだが、単結晶よりも低損失で効率のよいセラミックレーザーを発表した。この発表データはそれまでの常識を完全に覆すものだったので、世界を驚かせた。とくに米国のDOD(国防総省)は神島化学から1000個のサンプルを取り寄せ全米の研究所に配布して電通大/神島グループの発表データを再検証させた。1年のテストですべてが正しいことが検証され、セラミックレーザーは一躍ひのき舞台に躍り出た。
なぜ、セラミックなのに単結晶よりも損失が少なく効率のよいレーザーになるのか。従来のように酸化物粉末を焼成して作る手法では、結晶粒と結晶粒の境界をガラス質でつないだような構造になっている。境界層と結晶部分の屈折率が違うので、光が散乱してしまう。そのため、たとえ結晶部分に泡(ボイド)のない透明なセラミックでも単結晶よりも効率のよいセラミックレーザーなどできるはずがないと考えられていた。
しかし、新手法ではナノ結晶同士が、焼成の過程でちょうど二つの水滴が接したとき表面張力の働きで一つに合体するように、無理なく大きな結晶として合体していく。このため余分な内部応力などが発生せず、大きなロッドを作っても光学的に非常に均質性の高いものができる。また、境界層も厚さがオングストロームでレーザー光の波長より2ケタ薄く、屈折率の違いは問題にならない。
これに対して、単結晶のほうは、結晶として成長していく過程でさまざまな欠陥や内部応力が発生し、光学的にひずみのない大きな結晶は作れない。このため10cm超える材料では、出力、効率ともセラミックレーザーのほうが優れているという。
セラミックレーザーがキーテクノロジーに
セラミックの良さは、単結晶に比べて安くでき、また、単結晶では不可能な大きなサイズにできることだ。単結晶よりも性能のいいセラミックレーザーが安価にできるようになれば、高出力の固体レーザーはすべてセラミックレーザーに取って代わりそうだが、そうはなっていない。それは産業用レーザー加工機などの分野では、本体は2000万円してもレーザーロッドの価格は高々数万円で、より安価にするメリットが少ないためだ。
しかし、従来の単結晶レーザーでは不可能な先端分野の応用領域で、セラミックレーザーがキーテクノロジーになりそうだ。
そのひとつは米国防総省の戦略レーザー装置。MW出力のレーザーでミサイルを撃ち落とそうという計画で、これまで化学レーザーで進めてきたが、セラミックレーザーに切り替えた。2009年初めに出力100KWのセラミックレーザーを開発したと発表したあと、非公開になった。もう一つはレーザー核融合研究の分野。現在使われているガラスレーザーの代替としてセラミックレーザーが候補になっている。
さらに、植田教授が現在最も関心を寄せているのがレーザープラズマ加速の領域だ。これまで長さ数十キロの大規模なマイクロ波加速の加速器を建設しなければできなかった高エネルギー物理を、卓上で実現しようとするものだ。それには超高出力のレーザーが要る。世界のすう勢は当面100PW(ペタワット=10の18乗(W)ワット)の超高出力レーザーの開発を目指している。それができれば10の23乗W/平方センチメートルくらいの光強度が現実のものになり、光から新しい粒子を作る、宇宙のビッグバンと同じことをレーザーで実現する可能性が見えてきたという。まずは超高出力でパルス幅フェムト秒のレーザーを実現しなければならないが、それにはやはりセラミックレーザーしかないと植田教授は見ている。重力波観測の夢から生まれたセラミックレーザーだが、今度は宇宙の誕生を直接実証する夢に向かって、新たな進化が始まりそうだ。来年(2010年)はレーザー誕生50周年。植田教授の周辺は一層にぎやかになりそうだ。
(2009年8月)
- 注1:神島化学工業がサンプルを提供し、レーザー新世代研究センターがデータを提供するという、いわば企業の技術と大学の知が結び付いた共同研究で、両者の間にはお金のやり取りは全くないという。
- (新しいウィンドウが開きます)レーザー新世代研究センター