ユニーク&エキサイティング研究探訪
No.02 豊田研究室の量子ドット利用太陽電池の研究
次々世代太陽電池―夢の超高効率実現への挑戦
電気通信学部
量子・物質工学科
豊田 太郎
教授

電気通信学部
量子・物質工学科
沈 青 助教

豊田研究室とジャウメ1世大学(スペイン)との研究交流課題「ナノスケールで設計された低価格半導体ナノ結晶増感太陽電池の研究」が、このほどJST(科学技術振興機構)が実施する戦略的国際科学技術協力推進事業「日本―スペイン研究交流」に採択された。この半導体ナノ結晶(量子ドット)増感型太陽電池研究に関連しては、同研究室の沈青助教の研究課題「半導体量子ドットの多重励起子生成と太陽電池への応用」が、先ごろ同じJSTの平成21年度戦略的創造研究推進事業(さきがけ 注1)に採択されており、豊田研の太陽電池研究に弾みがつきそうだ。
低炭素社会を実現するクリーンな電力として、あるいは将来の化石燃料の枯渇への備えとして脚光をあびる太陽電池だが、現状では多くの課題を抱えている。大きな問題の一つは、現在実用化されているシリコン太陽電池が、電池そのものを作るのに膨大な化石燃料エネルギーを使ってしまい、有効稼働期間中に使っただけのエネルギーを生み出せそうにないことだ。それに材料コストも高く、いずれシリコンも資源枯渇問題に直面する恐れがある。そこでもっと省エネで安くできる次世代太陽電池を開発しようという動きが、世界中で活発化している。
半導体ナノ粒子を増感剤に使う
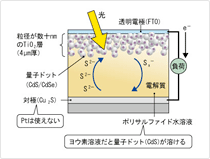
- 色素増感型太陽電池の構造イメージ図
次世代、次々世代太陽電池の候補はいくつかある。豊田研究室が取り組んでいるのは、量子ドットと呼ばれる半導体ナノ粒子を増感剤に利用する太陽電池で、次の世代の有力候補の一つだ。いくつかの壁を乗り越えられれば、シリコンに比べはるかに安く、高効率の太陽電池ができる可能性を秘めている。量子ドットを利用する太陽電池は、構造的には、十数年前に登場した色素増感型太陽電池(参考図)のそれとほとんど同じ。つまり、太陽光が当たる側の透明電極裏面に粒径数十nmの酸化チタン層をつけ、その酸化チタン粒子の表面に半導体量子ドットを化学的に付着させる。その層が電解質を介して対極と向き合う構造だ。光が当たって励起された半導体量子ドット中の電子が酸化チタンを介して透明電極に移動し、負荷を介して対極から戻り、電解質の中を移動して元の量子ドットに戻るという動作で電池として機能する。
色素増感型の最大の問題は寿命が不十分なこと。酸化チタンは光触媒として使われているほど酸化還元反応が強く、有機色素を分解してしまうためだ。
そこで豊田研究室は以前から扱っていた半導体量子ドットを色素の代わりの増感剤として使えないか、研究を始めたという。
半導体量子ドットを増感剤に使う太陽電池が有望視される理由はいくつかある。最大の理由は、量子ドットに光が当たると「多重励起子生成」(MEG)が起こるからだという。励起子とは電子と正孔が対になったもので、半導体に当たった光のエネルギーで生成される。通常は1個の光子で1個以下の励起子しかできないが、CdSeなどの半導体量子ドットでは複数個の励起子ができる。光で励起された電子を取り出すのが太陽電池の原理なので、それだけ効率の高い電池ができる可能性がある。
さらに、半導体量子ドットは(1)光の吸収係数が色素に比べ10倍ほど高い、(2)粒径によって波長の違う光を吸収する。つまり大中小の量子ドットをうまく分散して使えば、赤外光から紫外光までを発電に使える、(3)イオン性結晶で、電気的な結合力で結晶が出来ている。結晶の中にプラスとマイナスのイオンが作る電界があり、それが光エネルギーによって生まれる電子を動かす駆動力になる、などの特徴がある。
このような理由で量子ドットを用いた太陽電池は、理論的には44%という高いエネルギー変換効率が可能だという。
エネルギー変換効率3.8%を実現

- 半導体ナノ材料作製
しかし、研究に着手した当初は、全く問題にならない低変換効率のものしかできなかったという。今春、ようやく3.8%というチャンピオンデータを対外発表した。対向電極に白金ではなく硫化銅(CuS)を採用したり、電解液を工夫したり、量子ドット表面を硫化亜鉛(ZnS)の原子層でコーティングしたりといった試行錯誤を重ねて達成した。3.8%という値は、半導体量子ドットを利用した太陽電池としてこれまで発表された中では、今のところ世界で最高の効率だという。
同研究室の当面の目標は、5%を超す変換効率を達成すること。そのためには、「いかなる物理現象が変換効率を決めているのか見極めることが大事」(豊田教授)だという。光で励起された量子ドットの電子が移動するにはいくつかの境界面を通過しなければならないが、変換効率に悪さをしているのは、どの境界面かなどをこれから突き止めなければならない。
たとえば量子ドットの特徴である多重励起子生成も、単体では確かに起きているが酸化チタンナノ粒子に付着させると起こらなくなるという。量子ドットと酸化チタンの境界面に何らかの問題がある。境界面としてはさらに対向電極と電解液、電解液と量子ドットの境界面がある。
豊田研究室では今後、フェムト秒(10のマイナス15乗秒)という極短時間にこれらの界面でいかなる物理現象が起きているのかを見極める一方、太陽電池デバイスとしてどこでエネルギーを失っていくのか、マイクロ秒とかミリ秒などの時間域でも評価していくという。
なお、半導体量子ドットとして使っているカドミュウム(CdSeやCdS)が有害だと問題視する意見もあるが、豊田教授は意に介していない。量産ではなく、物理現象を解明するためのモデル材料としてCdSeなどを利用しているためだ。将来的には、CdSe量子ドットで判明した物理現象を基に材料設計を考察し、安全な材料を探索する予定。
次々世代太陽電池の開発を巡っては、世界中で息詰まるような開発競争がしばらく続きそうだが、変換効率5%超の1番乗りを期待したい。
(2009年11月)
- 注1:「さきがけ」は若手研究者の研究活動を支援するJSTのプロジェクト。ここで採択された研究者は。研究総括責任者や領域アドバイザー(複数人)などと一緒に年数回の合宿形式の研究発表などを通じて同じ研究領域に集まった研究者と交流・触発しながら3年間研究に取り組む。
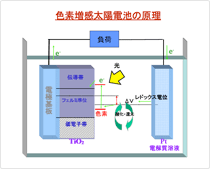
- 色素増感型太陽電池の構造イメージ図
参考:色素増感型は、有機色素を付着させた太陽電池で、動作原理は銀塩写真に近い。写真の場合は光で励起された電子が臭化銀などの銀イオンを中和するが、電池の場合は光励起された有機色素の電子が酸化チタンを介して電極に移動して、負荷を通って対極から戻り、電解質を介して元の色素に戻る。量子ドット増感型の構造は、この図の色素を半導体ナノ粒子(量子ドット)に置き換えた構造に似る。
酸化チタンは安く簡単に製造できるため、次世代太陽電池の有力候補の一つと考えられている。
色素増感型太陽電池が、一躍注目されるようになったのは、スイスのMichael Grätzel氏が1991年に7%を超える光電変換効率を実現したため。有機色素を付着させる酸化チタンを、粒子状にして色素の付着する表面積を大きく増やすことで、高効率を実現した。現在12%台のエネルギー変換効率を達成している。
